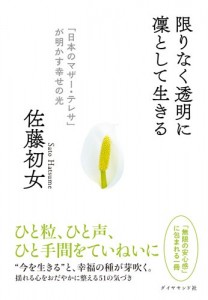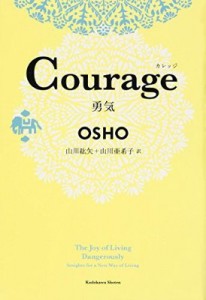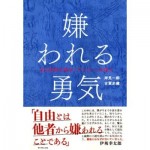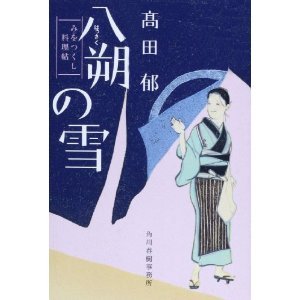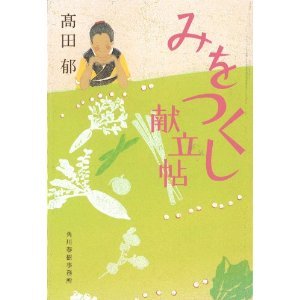青森県弘前市で「森のイスキア」を主催されている、
佐藤初女さんの最新の著書
『限りなく透明に凜として生きる
――「日本のマザー・テレサ」が明かす幸せの光』
を最近、少しずつ読んでいる。
この本では、初女さんが生きるうえでの大切なポイントを
いくつか挙げておられて、私はその中でもとくに
いのちのうつしかえ
という言葉に、とても惹かれている。
私たちは食べ物をいただいて生きる存在であり、
その食べ物とは、もともとは、他のものの命である。
私たちはその命を、食べることで移し替えていただいて、
生きさせていただけているのだ、と。
これはね、本当に、そうだと思った。
日本人として「いただきます」の習慣があるおかげで、
すんなり腑に落ちたのかもしれない。
毎日、私たちは、他の生き物から命を移し替えさせていただけているのだ。
私たちは、他のほ乳類同様、生態として
そういう生き方の道を選んだ「生き物」である。
で、ここで少し、話が変わるのだけれど、
えーと、残忍な表現も使うので、不快に感じられる方がいたらどうかお許しください。
あくまでも、私の主観です。
私は、動物を食べることを「残酷だ」と非難する人の気持ちが、
実はあまり、よくわからないのです。
というのも、そう言っておられる方々のほとんどが、菜食はされているから。
まず、生態系としての「人類」の位置を考えるうえで、
人類に近い「種」を食べることは必ず身体に不調をもたらす、という説があって、
そのことは「狂牛病」として知られる牛海綿状脳症(BSE) でも
一部、実証されたように思う。
ゆえに人がね、人間(ごめんね、あえて書いてみるよ)や猿を食べるのは、
同様の理由から、生物学的に「まずい」気はするの。
では、そういう面で見た場合、
同じ「ほ乳類」は、どこまでの種が問題となるのだろうか。
たとえば赤身肉には人体に対する発がん性物質が云々、というのも、
じゃあ魚介類や鳥類や、少なくとも植物に発がん性物質が含まれていないと、
誰が完全に証明できるのだろう。
そもそも「がん」自体の発症メカニズムが完全に解明されていない以上、
今、見つかっている発がん性物質だけが、問題ではないのかもしれない。
統計上の数字だけに踊らされ、不安を感じているのではないだろうか。
それに食べ物のせいで現れる「かもしれない」発がん性よりも
菌やウイルスや毒素のほうが、急性症状として
かなり命に関わると思えるし、それはいつやってくるかわからない。
縄文時代には、鹿やウサギやイノシシ、モグラ等の動物や、
もちろんかのナウマン象も食べていたらしい形跡はあり、
貝塚にはそれらの骨もあるらしい。
で、その縄文時代って、1万6千年は続いたらしい。
もちろん植物も採取していたよ、と。
さらに、総じて縄文人自体は短命(とくに赤ちゃんのときに命を落としやすい)。
ならば弥生時代の稲作でいきなり長寿になったかと言うと、今のところ
そういう明らかな証拠もないそうだ(これまで見つかってきた遺骨にも
個体差があるのでは、という説とかね)。少なくとも「肉も」食べてはいた、
そしてそれが理由で滅んだのではなかった(現人類はまだ、2000年だか
3000年、縄文人のほうが現状では長く繁栄し続けたことは事実)。
うん、まだね、こういう医学面・生物学面で判明しつつある
何らかの問題ゆえという話なら、わかるのよ。
でも「倫理上」の「ほ乳類はダメ」というのって、
ただの「現代的な概念」じゃないのかと。
命をとるのが「残酷だ!」という人は、
なぜ、植物を食べるのは平気なのだろう。
若葉は「ベビーリーフ」という名もあるくらい、
まさに植物の赤ちゃんなのに、それを新鮮だと喜んで食べていないか?
しかも生のまま、つまり植物が生きている状態でばりばりと。
実をいただくというのは、つまり次世代のために植物が作った
命のもとと、それを守る包みの部分を、勝手にもぎ取って、
次を生まれさせず(まともな種にもさせず)奪っているのではないのか?
根を下ろしてまるまると育った大根を、
その、大根たちの生活空間(土の中)から勝手な都合で引っこ抜き、
次の葉っぱ一枚さえ、その根からは生まれさせないやり方で、
まさに根こそぎ奪っていることは、事実ではないの?
何度も生えてくるハーブ、たとえばネギを、飼い殺しのようにしていないか?
その身体や腕をもぎ取っては、足(根)だけ残して、
さあ、もう一度身体を再生しろ、
そうしたらまた食ってやる、と言って切断していないか?
しかもそのネギが、我が身を切られて辛みを増すのは、
ネギの「生物学的な防衛反応」だけれど、
それを喜んで薬味にしているのではないのか?
なぜ、菜食することは残酷だと、
動物を食することと同様に捉えられないのだろうと、
私にはそのことが疑問なのである。
私たちはそもそも、そんな崇高な生き方ができる生態系ではなく、
他の命をいただく存在なのだ。
それを、菜食は許せて肉食はダメ、って、なぜ勝手に決めていいのだろう?
しかもなぜか、ビーガンの方々のなかには、大上段に構えて上から目線で、
健康云々等からも動物を食べることを非難する人の率も高いのだけれど
(全員ではないから比率ね)、それを言うなら、
わざわざ葉をちぎって、ひからびさせて発酵させる、
つまりさらに、微生物の生きる力まで「薬効だ」と言って
湯をかけて殺して飲むのが「お茶」だったりするよ?
煮立たせた湯に葉を落とすのが「生ハーブティー」だよ?
ゆで野菜、焼き野菜はどうなの?
動物が可哀想と言いながら、では赤い血さえ見えなければ何をしてもいいの?
なぜそっちは残酷じゃないのだろう?
あとね、猟師生活を選んだとある女性ブロガーのことを
罵倒している人たちもいるけれど、
自分が植物の命をあらゆる方法でさんざんに「もてあそんでいる」かもしれない、
そういう可能性に気づいておられないのであれば、その方々よりも、
「ひとつの命」としっかり向き合って、それを尊び、ありがたく「いただいて」、
骨も皮も無駄にしないで使おうとする彼女のほうが、
「生命体」の一人としてよほど崇高な気がするのは、
私だけなんだろうか……。
と、口調が強くなってしまったけれど、
私にはそういう主観があるがゆえに、別に肉食だろうが菜食だろうが、
「いのちのうつしかえ」をさせていただけている、という初女さんの謙虚さに、
すごく納得がいったのですよ。
だからこそ、おいしくいただかないといけない、と言って、
「いちばんおいしくいただける方法」を、ゆで方ひとつから、気をつけていく。
それでもまだ「おごり」の部分は残るのだけれど(いただく、というのは
言葉としての逃げであり、奪うことに変わりはないのだ、
と言われたらその通りなのだ)、
そういうこともふまえたうえで、それでも「いただいて」生きていくのは、
常に、食べ物に対する「ありがたさ」を、感じられる方法だと、
私には思える。
あ、追記しておきます。
こう書くと鬱の方は、植物にさえ迷惑かけられないと思って
不食になりたいかもしれないけれど、
これまで移し替えていただいた命のことも考えて、
上手に生きられない、ということを「生命」の問題とは
きちんと分けて捉えてくださいね。
あなたは生命の一つとして生きていっていい存在だから生まれた、そのことは
鬱になったあとでも、まったく何も、変化していません。
上手に「暮らしていけない」ことについては、回復ができるのです、
あなた自身が。まずは気持ちのうえで休むことから、始めてくださいね。
もうひとつ、この本には「透明になって生きる」ことについても書かれていて、
まだ、最後までは読んでいないのだけれど、
人としての謙虚さ、ありがたさ、を、知ることのできる本だと思えている。
そうした、人としての大切なものへの気づき、
その一端になればと思い、紹介してみます。
本の紹介だというのに、熱めの書き方して、今日はごめんなさいね。
例によって短縮URLの、アフィリエイトなしリンク、張っておきます。
『限りなく透明に凜として生きる――「日本のマザー・テレサ」が明かす幸せの光』
佐藤 初女 著 ダイヤモンド社 刊
¥1,280
http://ow.ly/OTFYy