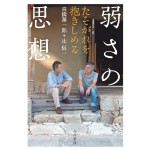そして後編からいきなり「ですます調」をやめます、私。
すみません、以降はそれだと書きづらいので(;^_^A)
でも最後のほうには戻るかと(笑)。
辻さんは「スローライフ」を提唱されてきた方なので、
グローバル化する(そして弱肉強食・肥大・勝敗によってしか成長できない)
市場経済の限界などについても言及されているのは知っていたけれど、
弱さの「思想」って何を表しているんだろう、と思っていた。
お二人の、面白いわ興味深いわ(笑)なトークが進むうちに、
そうした競争原理主義社会の「今までの価値観」って、
本当にひっくり返されてきてるんだな、
しかもあくまでローカルに、世界中のあちこちで、ってことがわかった。
で、実際この書籍は、社会論や思想論だけでなく、
いろいろな方面で起こりつつある
そのあちこちの例をも、紹介しているのだ。
老人たちが原発反対運動を「楽しみ」つつ自然に支えあう過疎の村、
子どものホスピス、障がい者こそが中心で発展してきた街、
「居場所がなくなった人たち」がやってくるコミュニティ的組織など。
それらはすべて、市場経済の競争原理の世界には「いない」人たちで、
世間ではこれまで「弱者」扱いをされてきた人たち。
日本で言えば、中央集権で「切り捨てに遭ってきたミジメな」と
形容されている「はず」の人たちだ。
でもそこに、新しい「世界」が確かに生まれている。
それは本来、人間が「持っている良さ」のひとつ、
多様性(ダイバーシティ、diversity)にも基づくものであり、
しかも「最弱の者たちが影響を、周囲に自然に与えて、
他者の価値観をひっくり返す、それもいい意味で」
ということが起こっている、と。
まもなく亡くなることがわかっている「子どもホスピス」の
子どもたちに見つめられて、自身の生き様を振り返らずにいられない親。
親の落ち込みがいちばん心配、と優しく話す子どもたち。
そこは静かで明るい現場。生と死がつながっている場。
しかも、もっとすごいなと思えたのが
子どもが亡くなったあとの家族が「生き直す」ためにも、
その子どもホスピスは役立っているのだ。
そうした子どもたちや家族が集まれる、そこにいられることで、
自然に、グリーフ・ケア(悲しみを癒し、立ち直るケア)の
役目も果たしている。
今までの社会では「切り捨てられてきた」人たちが
お互いの居場所を作り合える。
「助けられる・世話になる」のが絶対に嫌なおじいちゃん、の話も出てきて、
でも「おじいちゃんのほうが助けてあげられる」部分があれば、
支え合って生きる場所が生まれ、うん、ただそれでいいのだ、という事実。
効率化の正反対であるとして、できるだけ排除されてきた多様性を
弱者の側が「よいもの」として扱い、情報もよい意味で開示する。
隠さず示すことで「いわゆる『強者の立場』の者」にさえ
影響を与えられるほど、
今まで忘れ、切り捨てられてきた「良さ」を、示すことができるのだと。
しかもそれは、人間存在の根源に関わっている、と。
ほかにも、性差の違い(私はこれ、個人にもともと内在している
男性性と女性性のバランス、にもつながる内容だと思える)、
フォース(外の力、どうしても奪い合い・示し合いになり上下が生まれる力)と
パワー(個人が内側にもともと秘めているそれぞれの力)の違い。
障がい者が中心にいることで、街のみんなが人間的な豊かさに恵まれ、
住みやすくもなり、ゆえにその国で「住みたい街」として認識されていったり。
しかも自発的に「そうなっていくがゆえに、延々と試行錯誤していく」ものは、
支配の有無や勝ち負け、効率、とはまったく別の「価値」を生み出すのだ。
先日、NHKの「News Web」でも「ソフトヤンキー」という造語が
紹介されていて、それは地元を離れない、
上下関係でも礼儀正しく、優しさもある、でもヤンキー(笑)な
若者たちを指すのだが、こういうあり方って、
まさに「(中央などで目立って)成功して勝者になるのがすべて」とか
「これだけが正しい、かつ強い権力、あとは負け」みたいな影には
おびえないでいられると思える。
そしてそれを、今までは「脱落」と呼んできたけれど、
じゃあ実際、本当の「勝者」、楽しくて幸せで気楽で、
夢中になれる子どもの遊び的な部分もゆるされていて、
変なプレッシャーも受けないで済むのはどっちだろう? と。
社会的な成功って、最終的にそういう楽しみを味わうために
「まずこの壁の乗り越えを達成すべき」みたいに言われてこなかったっけ?
でもさ、今まで言われてた「この壁」って、どこまで、あるいは必要なの、本当に?
私が「私のようなタイプは、鬱になって、結局よかったのかも」と
これまで捉えてきた部分が、見事に「社会に溶け込みつつ変えていく
新たなパワーのひとつ」として、多角度から紹介されているのだ。
くだらない縛りはないけれど、そこでは管理もされないから、
「何も考えずに済むように、支配されてるほうが気楽」
というタイプの人には向かないのかもしれない。
でもその姿勢って本当は、自分の「パワー」を放棄してて
かなりいいように「こき使われ、利用されて」ますけど
(今、支配しているはずの側だって結局、自分の損得と脱落には
常におびえ続けていかなくちゃならないしね)、
あなたは、ホントにそれ「が」いいの? って、
死に向き合う子どもから聞かれているのかも……。そんな気がする。
弱いままでも、あるいは弱いほうが、この先の未来、
新しく楽しめる「いい生き方」を見つけられるかもですよ、マジで。
そこを、個人でも探せる時代になってきている。
すでに価値観のパラダイム・シフト(paradigm shift、
認識、思想、価値観などの劇的変化)は確かにひそやかに、
起こり始めているようなのだ。
もちろん、問題はそれなりに個々の現場で起こるんだろうけれど、
実は多様性って、すごい話だけれど「解決しないで内包」できちゃう部分がある。
あなたはそう、私はこう。違いがあるのね、うん、そうか。
じゃ、関わらないでおこう。
それはちょっとさ、周囲も実は、迷惑こうむるんだけどね……。
でもまあ……とりあえずいいか、和解、今は無理そうだから。
以上。
それでOK、画一的な絶対的「正解」はいらない世界。
その代わり、性悪……というか「自分だけがよければ」の
価値観のままだと、やがて居場所がなくなると思う。
周囲から攻撃されて排除されるのではなく、
本人がその状態では「安心して居られなくなる」から。
そういう距離感、人とのつながり方を作り出していく練習も
多様性を基本前提として自分がふまえることにより、
無理なく自然に、積めるだろうと思う。そこは新しい捉え方になっていくから。
あ、これは、ある生協さんの組織と仕事をして、
ちょっと実感してたことです。
ホント、だんだん、居場所を「自分で勝手に」なくしちゃうのだ……。
ま、ほかにも、アートな世界の方が「お手伝いしに」行ったはずなのに
ダウン症児の感性に打ちのめされる、その組織の話、
なんていうのも載っている。
弱者であるがゆえの素晴らしい影響力。ステキで面白そうでしょう?
てなことで。
病、障がい、介護、老い、などに、仕事やプライベートで
関わる方、またはご本人、はもちろんのこと、
ホール(全体的)な視野の「業務」や「生きがい」に関わる方、
まさにそういう生き方の方、
教育、環境、社会、経済系の問題に関わる方、
子育て中の方、この先、老いを迎える方、老後をお過ごし中の方。
なんだか、それぞれに楽しそうな生き方が、実はまだまだあり、
しかもそれが勝手に他者への貢献にも「ときにつながっちゃう」
ようなことが、いい感じでこの先、ありえるのかも。
その可能性を、社会が、世界が、はらみ始めているという、
その新しい視野の話。
温かく優しくしなやかな「希望」の、
さまざまな例と可能性をたっぷり示してくれる1冊です。
新しい形の「ステキなあり方」、ぜひ読んで、受け止めてみてください。
私は読めて、ホントよかった……。高橋さんの告知ツイートに感謝しますm(_ _)m
おかげで私、この先ワクワクしながら「成熟社会のたそがれていく側面」に
(自分の老いも含め)向かい合い、楽しみながら
「参加したいと思えたもの」には遠慮なく、加わっていけそうです。
また、アフィリなしのAmazonリンク張っておきます。
高橋 源一郎、辻 信一 著
大月書店刊 ¥1,728