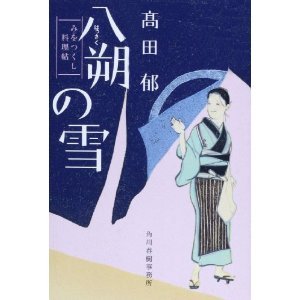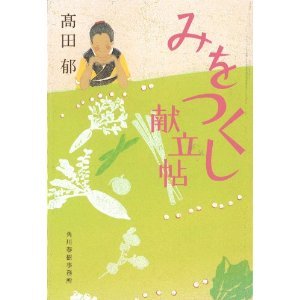小説を読んでいて、ときに食事の描写で「おいしそう!」と思うことがある。
お腹が空いているときはもちろんだが(笑)、そうでなくても
味が想像できるもの、和食、とくに時代物では、私はそうなりやすい。
確か最初は、池波正太郎氏の「剣客商売」か
平岩弓枝さんの「御宿かわせみ」のどちらかだったと思うのだけど……。
そこに出てる料理を実際に作ってみたのですよ、手順のわからないところは予想で補って。
するとね、やっぱ、おいしかったの。
和食なんて「さしすせそ」の調味料で基本、なんとかなるから、
材料と味付けの方向性がわかれば、適当にできるもので。
そんなこんなで、時代小説を読む際に、
自分がふだん使わない食材や味付けの料理が出てくると、
ついつい「作れそうかどうか」という視点が加わることとなりました(笑)
もともと池波センセの小説では、食べ歩きや創作に
チャレンジしてしまうオジ様たちがいることも知っていたので
うん、気持ち、わかるなあ、と思うようになった。
そうしたら! さすが、よくわかってる角川春樹事務所
(角川書店じゃないよ、春樹さんが出所前後に自分で作った出版社)。
たぶん女性層も狙って、料理人小説(捕り物やら人情もの)を
文庫書き下ろしで出し始め……私はまんまと、それにハマったのであった。
まず和田はつ子「料理人季蔵捕物控」(ただしこれは、
ストーリー展開のほうがだんだんおかしくなっていったため、
残念だったが途中で読むのをやめた)。
このシリーズいちばんのヒットが「だいこん素麺」。
刺身に付いてる「けん」くらいにだいこんを切った、でも長めにしたものを、
さっとゆがいて、梅干し+鰹節を酒でじっくり煮出したつゆ
(煎り酒、というらしい)をつけて食します。さっぱりまったり、ウマウマです。
あと、これはハルキ文庫じゃなかったけど、
宮部みゆきさんの小説(「ぼんくら」シリーズのどれか)で
「海苔の佃煮」のおいしさを語る人の下りがあって、
ふと、作れるのか? と思って調べたら!
ヘタにめんつゆとかも使わない、
激ウマなレシピが「クックパッド」に載っていたのであった。
おかげで私はもう二度と、桃屋、買えません(笑)
できるだけ細かくちぎった海苔を、
出汁と調味料でひたすら混ぜつつ煮詰めるだけなので、
海苔好きな人はチャレンジしてみてください。
とくに新海苔はウマイよ~(*^_^*)
クックパッド けゆあ さんのレシピ
http://cookpad.com/recipe/701441
そしてなんといっても、この小説。
大坂から江戸に出てきた少女が、
どんどん美味しいものを作り出してしまうだけでなく
家族愛やら友情やら恋愛やら、料理人としての生き方やらで、
降りかかりまくる「艱難辛苦(かんなんしんく)」を
次々と撃破していってしまう(笑)(でも主人公は途中でちゃんと悩み、迷う)
「時代物の昼ドラか!?」 と言わんばかりのその展開。
高田 郁(たかだ・いく)さんの「みをつくし料理帖」シリーズ。
この高田さん、出身がマンガ原作者だからでしょう、
ストーリー構成がとにかく精密。しかも視点が必ず温かい。
「みをつくし」シリーズは、8月に最終巻の第10巻が出る予定なのだけれど、
第1巻が出たときからたまたま読み始め、最初、3巻までは
「ん? 話が地味だよ?」と思って……。
次を読もうかどうしようか、迷ったほどだった。
でもね、実は3巻までの話は、ほぼ全部、「伏線」としての作り込み。
4巻以降からどんどん話が動き始め、その後は
「ど、どうするの、澪(みお)ちゃん!?」と思わず
人の良い主人公、澪を心配してしまうようにさえなったのでした。
それくらい途中から「次巻を待て!」的に、話を組んであるのだ……。
マンガ原作者、恐るべし(笑) 桐生夏生さんにも言えるけど、
マンガ原作って、実はすごい経験なんだな、と思える。
でね、しかも、出てくる料理がね。
これまた著者の高田さんがきちんと「実際に調理してみて、
おいしい」という味に仕上げてあり……巻末にちゃんと、
主要な料理の文字レシピが載っており……一時期休載された際、
次巻を待つ間に再現料理本も文庫で出て……。
これまでに私が作ってみた、澪の料理
(ちなみに、レシピ通りに作ると、とくに塩気は濃いめなのでご注意)。
●酒粕汁(さけかすじる)
(鮭、だいこん、にんじん、油揚げ、こんにゃく、白ネギ、
酒かす、味噌、酒、みりん、しょうゆ)、たまにカブやごぼうも投入
●鼈甲珠(べっこうだま)
(生卵の黄身の、味噌+みりんかす漬け。
卵黄を、みりん絞りかす+白味噌+赤味噌+みりん+酒に埋めて漬ける)
●だいこん油焼き
(半日干した半月切りだいこん、
ごま油でじわっと焼いて酒、しょうゆ。食べる際に山椒)
●ウドとワカメの酢の物、ウドとワカメの酢味噌和え、ついでに自分で
レシピ調べてウドご飯(昆布出汁+短冊切りウド+塩+酒でご飯炊く)
●菜の花飯
(昆布出汁と酒、塩でしっかり味付けしてご飯を炊き、蒸らす際に
塩ゆで→同じ味付け出汁に漬けておいた菜の花を混ぜる)
●忍び瓜……ゆでキュウリの三杯酢漬け
(麺棒で叩き、軽くつぶしたキュウリをなんと、さっと湯がき!
三杯酢+ごま油+唐辛子の合わせ汁に漬けて半日)
●里の白雪……すり下ろしカブの蒸し物
(カブに卵白と塩を混ぜて、湯通しした鯛にこんもりとかけて隠し、蒸す。
出汁+酒+塩+みりん+しょうゆ、にとろみをつけた「銀あん」かけてわさび)
……おかげで自分の食卓が、いかに楽しくおいしくなったことか!
たぶん今度の休みには、「レンコンの射込み」
(海老詰めて揚げる)が気になっていたので、
チャレンジしてみるだろうと思います。
あとついでに、山芋とカブと海老で作る「立春大吉もち」とか、
ごぼうの素揚げも……。はうう。楽しみ。
絞りかす系、好きなのです、っていうか、
そもそも糀(こうじ)、発酵ものLOVE。
昔は甘酒も味噌も仕込みました(笑)
酒かすだけでなく、京都や奈良でしか見かけたことのなかった
「みりんかす」が、まさか料理に使えるとは! と。
貯まっていた楽天ポイントでお取り寄せしましたさ、有機もの(笑)
鼈甲珠も酒粕汁も、はい、絶品でございました。
……てなことで。読んでるだけでも和食好きにはたまらない、
文庫書き下ろし「みをつくし料理帖」シリーズ、
現9巻+料理本1冊、でございます。
アフィリなしリンク、ご確認をぜひどうぞっm(_ _)m
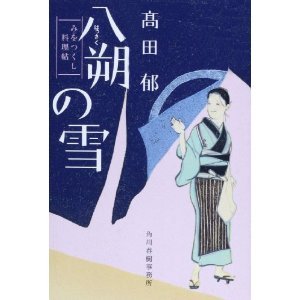
八朔の雪―みをつくし料理帖(第1巻)
高田 郁 (ハルキ文庫) ¥580
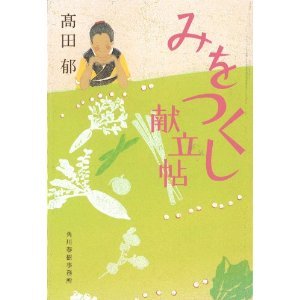
みをつくし献立帖
(各巻巻末に載っている
主要料理のレシピは
再掲載していないが、
ストーリーに出てくる
ほかのレシピを掲載)
高田 郁 (ハルキ文庫) ¥720