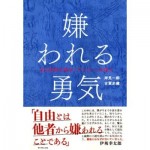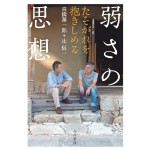最近拾ってきた「方向性」の情報で、
んあ? と「疑問に思ったこと」いろいろ。
その方向とは違うところへ進んでいくために、
今、何ができるか、を考える。
そのためにこうした情報を自分で整理し、
お知らせもしてみます。
話を始める前にお伝えしておくと、私は
民族や国籍などに関係なく「命」は大切だと思う者、
平和を「愛する」この国を、愛して誇りに思っている者、
そしてあらゆる生命は「自然から賜った貴重な贈り物」
だと捉える者、です。
この自然、という枠は、人の命だけでなく
地球のすべての命や、石や岩や水、気体、太陽や星々などまで含みます。
私には一切、それらの仕組みを作れません。
ゆえにありがたく、自分のために、自然と太陽の恵みや、
月や星座からの慰めや、他の生命体の「命」を毎日、いただいています。
ええ、植物も含め。
そういうスタンスからの情報提供として、お読みください。
まず、TPP。
メリットよりもデメリットのほうが多いな、と感じていますが
最近、驚いたのが以下3つ(これらの情報ソースは
いろいろ探しにいったんだけど、
日本語で書いてあるのがまだ少なくて……残念)。
米国企業から言いがかりのような形で他国企業が訴訟を起こされ、
しかもそれは米国内で審議されるため「米国側が必ず勝ち」になって、
負けた企業のほうは巨額の補償費用を払わされるという、
そのルール自体が一緒に入ってくる、らしい。
さらに次の2つも。
ひとつめ、遺伝子組み換え食材。なんとなんと、輸入の際に、
「組み換えなし」という表示が「された」ものを扱うことは、
TPPのルールで、逆に違反になってしまうらしく。
で、さらにBSE検査がまったく済んでいない牛肉も入ってくるそう。
狂牛病にかかっている牛の肉かどうか、
ロシアンルーレット化するの? じゃあ。
レストランとか、どうするんだろう、どうなるんだろう。
この関連の情報を追っかけていってさらに笑えた情報。
その遺伝子組み換え植物の「種子」を扱って
世界中でボロ儲けしている巨大企業、
米・モンサント社の社員食堂って、
遺伝子組み換え食材を一切、取り入れていないんだって!
さあ、なぜでしょうね?
日本のメーカーの、某パン製造会社の社長も、
自社のパンは絶対に食べないって噂、ありましたよね(笑)
次、防衛系行きます。
武器の輸出、部品の輸入で、今度は
EU&アメリカ&アラブ&アジアまで交え、
グローバルな「武器ムラ」の仕組みができつつあり、
実際に稼動も始めたいようです。
最近、海外へ行ってきている我が国の首相は、その外遊で
武器製造LOVE(ウチ、製造して売りたいよ!)の
日本の重工業系メーカー関係者をぞろぞろ引き連れ、
彼らとともに「国際的な安全に積極的に取り組みます」って、
各国を回っておられるみたいです。
「原子力ムラ」で資金稼ぐの、限界見えてきちゃったからね。
とはいえ「再生処理」「高速炉」は手放す気がない、
プルトニウム持ってないと、イヤだから。
その代償のひとつが、現在まさに、海外で働いている
国際ボランティア等の「命の危険性」(憲法の解釈を
変えるだけでも、もう、逆に命を狙われる危険性が
グッと上がるらしいですよ。実質、九条の放棄だということで
他国から、日本への不信感が高まって)と、あと少なくとも
自衛隊の若い隊員たちの「命の危険性」だそうですが。
アジアへ「お節介仲裁」しに行くと、結局は牛耳れると思ってるから
仲裁しに行きたいだけ、なんじゃないの? アジア版・米国の真似。
そのために少なくとも海外ボランティアや若者の命、
使いたい放題ってか?(少なくとも、と、何度も
わざわざ注釈をつける理由、おわかりですよね。
解釈変更「し過ぎて」他国に「強く」貢献することで、
国際的な過激派が「日本は危険」と解釈したら?
テロ? 誘拐や拉致? さて他には? しかもどこでそれを?)
アメリカ人が日本人の命を守ってくれてるのに、
日本は何もしないのか、って?
うん、じゃあ日本の領海内、または海外でも、
相手が「先に」攻撃してきたときだけ、とか、
そういう「他国から誤解の起きようもない」確実な限定条件、
せめてつければいいんじゃないの?
そんな方向性、調べても非自民の小さいところ以外
ほとんど出てこないんですけど、現状で。
それに米国が、日本での軍事系を手放すと本気で考えるのかな?
巨額のお金、払ってるんでしょう?
すでに巨額のお金を「投資してきて」
何十年も、米国に「守ってもらう」体制を作ってきた、
じゃあ、自国防衛という形で今回、それまでの金を
どんどんドブに捨て始めて(実はその陰でずっと、
米国から多額の資金提供を個人的に受け取りまくった政治家も、
多数存在してきた「らしい」のに……って
これ、あくまで隠してるそうで
ここ数年、アメリカ側の資料公開によって
それがバレつつあるんだそうですね~)、
かつ、今後は米国からあんまり(ってどの程度なんだろう)
守ってもらわなくてもいいようにする?
いや、もうすでに、裏の関係がズブズブすぎるから、
そんな簡単に縁を切れるはずもなく、
そこを無理やり縁切ったら、それこそいろいろ孤立しますよ、
経済面とか食料とか意地悪されるかもですよ、今の段階ではまだ。
本当にそもそも、ですよ、これだけ今までお金を出してきた国を、
米国があきらめると思う?
敗戦国という扱い、いまだに言われてしまうわけですよ?
実際「第二次世界大戦の陰影」が残っているから、
チベットやウイグルが国際的に「あのまま」にされている。
だってあそこは隣の国の「自治区」だから。
ウチでは、自国内で血を混ぜることを選びます、以上。
「内政不干渉」は、英国やフランスや米国が、自分たちも
突っ込まれたらめちゃくちゃ困るから(覚えてますか~?
フォークランド紛争なんて1982年、結構、最近の話なんですよ~)、
国際的には何も、言われていない。
いまだに、そうなのです、まだ。残念ながら。
で、日本に攻めてくるのって、
もうウイグル並みの危険度があるの?
内政不干渉、と世界中で認識されるほど、
日本は現在、国際的には隣の大国の「自治区」扱いなわけ?
お隣って、挑発してきては「攻撃されるの」待ってるわけでしょ、
本気で相手と同じ発想レベルまで落ちて、それに乗るの?
これは個人的予想ですが、始めたらたぶん延々、
嫌がらせなゲリラ戦、展開されますよ? はい、テロ中心でね。
いったん始めてしまったら、止まりませんよ、そのテロ。
かつ他国の過激派も、儲かりたいから絡んでくるだろうし。
だって、お隣の政治・軍事的仕組みは今のところ、
個人の、家族や親族の命や生活を丸ごと人質にしてから、
その個人を部下にして、命令出せるんですよ?
それで、日本は「勝つ」ところまで、たどり着けるのかなあ? 本当に。
……ま、こういうこと書くと、
非国民、とか言われるんだろうなあ(笑)
別に米国LOVEでもアジアLOVEでもないんだけど。
国としては日本LOVEなんだけど。
「堂々と主張する」、その方向性が違うと思うだけ……。
あと、福島県の子どもの甲状腺がん、発表になりましたね。
甲状腺がんと診断が確定した子ども50人、疑いありは39人。
国立がん研究センターなどの統計では、これまで
10代の甲状腺がん発症率って、
100万人に1~9人程度(バラつき多いな)とされてきたそうなのに。
福島県では、37万人を対象に検査してきて、
今のところ、29万人のデータがまとめられ、その結果が50人。
残りの人は不明なわけだから、まあ、今は37万人として
単純に2.7倍してみましょうか。それでも
100万人のうち135人くらい、になってますけど?
え? 100万人に1~9人程度、だったはずなのに?
しかも3年過ぎた段階で、もう?
チェルノブイリでは4~5年後から甲状腺がんの
発症率が急増したそうですよ……?
でも「直接的な健康被害は出ていない」って
この前も、田植えされてましたよね。
まあ、因果関係は「証明されない」わけですがね、
まだ、というか、果たしてこの先……。
ある一人の、かけがえのない大切な子どもの命に対する
「苦しみ」が、ひとつの県だけで、もう
50軒分、50家族の分、すでに発生している。
これから一生、ずっと怖いであろう、その苦しみが。
でもって福島第1原発の、3号機の格納容器、
破損していたらしいですね。
格納容器の破損は、とてもとてもヤバイ! と言われてたはずなのに。
このままでは地下水、汚染されちゃいますね、さらに。
地下土壌だけでなく、海へも流れていきますね。
今、汲み出してる(そして機械が壊れたりしてる)汚染水、
それどころじゃない、比較にならないくらい
高い濃度の水が流出するかも、と、恐れられているのですが?
人が絶対に入れない格納容器の外側の部分、
どうやって調べて、どう防いでいけるのでしょう?
コントロール、確か、完璧なんですよね?
……キツイ現実。
ねえ、これらの「舵取り」の責任、誰が引き受けられるの?
どこの誰が代償、払うの? しかも命で、ってこと?
自然まで含め全部、だよ?
これも張っておこうかな。NHKが残してくれている動画記事。
「人の価値は、何を言うかでなく、何をするかで決まる」
1992年、12歳のとき、
どうかあななたち大人が、私たち子どもの手本になってください、と
リオの国連会議で訴えたセヴァン・スズキさん。
もしよかったら下記の、あのときの彼女の発言も聞いて欲しい。
軍備より先に、お金を使ってやること、あるんじゃない? やっぱり。
http://cgi4.nhk.or.jp/eco-channel/jp/movie/play.cgi?did=D0013770650_00000
てなことで、どうしても原子力関連事業は放棄したくなくて
しかも軍事系も始めて、国民(と他国の人間や地球の自然)の
命よりはずっと、個人でも党でも企業でも、
儲けるほうが大切な「方々」に向け(ある一党の方々だけを
指しているのはございませんことよ、それではこと足りない)、最後に。
「広告批評」で昔、掲載されたというこのグラビアを
お贈りしたいと思います。これ実行してくださるなら、
もはや「個人的信念」の違い、になるから、
私もまだ、検討の余地、できますよ~♪
ある個人の方のブログ記事なんですが、
天野さん×浅葉さん×糸井さんでつくったらしい
このポスター、私、好きです(笑)
命のレベルで、大好き♪
◎不定点日常観察日記